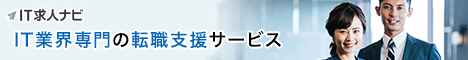・カラーを勉強して色彩センスを上げて仕事に活かしたい
・イラストや資料作成、デザインのクオリティを上げたい
といった方向けの記事です。
こんにちは!マサカ(@masaka_blog)です。
デザインに興味がある、色彩検定を受けるか検討中の方に今回の記事が手助けになれば幸いです。
色彩検定へのマサカの感想は
「色の勉強未経験・学習中の人はスキルアップにはよい資格です。就職に有利にするために取るならオススメしない」です。
その理由と、メリット・デメリットについて詳しく5つの項目で紹介していきます。
著者(マサカ)について
現在:色彩検定2級を取得。僕は学生時代からイラストを描くのが好きで、
デザインや色へ興味があり色彩検定の資格を取得。写真、印刷業界に就職して、
現在は知識を活用しDTP・WEBデザインや動画編集を担当。
今回の色彩検定に関する記事は、
フリーランスエンジニア・クリエイター向けの案件情報を発信している「Freelance hub(運営会社:レバレジーズ株式会社)」様のサイトで、ご紹介いただきました!
■freelance hub掲載記事
「Web業界で活かせる資格は?スキルアップにもつながる資格取得の体験記事まとめ」記事内
【実体験あり】デザインのための色彩検定合格のメリット・デメリット(マサカブログ)
色彩検定を取得するメリット・デメリット

はじめに色彩検定を取得することでのメリット・デメリットを紹介します。
実際に試験勉強する前に取ったことで、自分がどう変わるのか気になりますよね?
色彩検定を取得するメリットとは?
◎カラーコーディネートの知識を論理的に理解。
◎ファッション、インテリアデザインを学べる。
◎色の知識を勉強することで色彩センスが上がる。
色彩検定の2級を合格した時には間違いなく、
今まで何も色の知識を持っていない状態だった人は、カラーコーディネートの個人スキルがグンと上がります。
理由は
勉強の中で色の色相環とトーンの種類という項目を覚えることになります。
学習で色相関とトーンの図が、頭の中でイメージできるようになると色の選び方が変わります。
たとえば
「黄色に合う色はこの色で、面積を考えるとこの配色か」
と条件や使う目的を考えて思考ができるようになります。
-

-
デザインとイラスト制作で役立つカラーの配色方法まとめ【色を勉強】
デザインって苦手でいまいちカッコよく・かわいくならない…。フォントや背景の色って何をえらべば良いか悩む。色を組み合わせる時の相性がわからない といった経験はデザインやイラストを制作する中でありますよね? そこで今回の記事でご ...
続きを見る
イラストやデザインをしている人は、PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTと
いった画像編集・イラスト制作ソフトのカラーパレットの選択・画像編集を効率的にできます。
色彩検定を取得するデメリットとは?
◎採用、面接で有利に働かない
◎資格所有してもインパクトが弱い
残念ながら色彩検定の資格は、国家資格など高難易度の資格と比べると取得で大きく採用では有利に働かないです。
マサカ自身の実体験ですが、
正直な所で言えば色彩検定の2級を取ったとしても、採用の面接で
「色彩の勉強をしていたんだな」と思われるくらいでした。
実際に会社採用の面接でも「ふーん」という感じで対応をされましたね。
新卒採用、転職や権威性のために資格取得に求めるのであれば、
別のIT系や国家資格の取得に勉強を注ぐのが有利になり健全かと思います。
自分自身の目指したい将来のキャリアと、今のスキル向上の手段として考えるのがおすすめです!
色彩検定の資格の種類をそれぞれ解説【2級・3級】
そもそも色彩検定の資格ってどんな資格?
色彩検定は、色全般の知識からその配色方法までを学べる資格です。
現在、試験は毎年2回(6月と11月)実施。(1級は11月の年1回)
残念ながら新型コロナウイルスの影響で2020年6月の試験は延期となりました。
色彩検定は1~3級までの3つの階級があります。
その中で色彩検定と言った時に一般的なのは2級・3級です。
1級は高難易度で、記述以外に実技の試験があります。

色彩検定の試験内容は
「色の名称、配色方法、ファッションでの活用方法、インテリアデザイン全般」など幅広く出題されます。
◎試験合格基準
「各級満点の70%前後の正答率」で合格。
【各級】
3級では色彩学の基礎的な知識を学ぶ入門的内容
2級では3級範囲を深化させ詳細に学ぶ発展した内容
1級では2.3級範囲に加えて 色彩の専門的な知識&技能が必要とされる内容
実際に取得した感想では、
もし仕事に活かしていくことを考えるなら2級を合格できるように勉強するのが良いと思います。
試験の難易度ですが、
結論としては「独学で1ヶ月真剣に勉強する!」
これで2級は合格できます。
基本は独学で公式テキストや専門書籍で勉強する。
マサカはアプリを使って、出題される色を覚えたりしました。
全くの未経験からの方は仕事や学校帰りにスクールなどで、
勉強機会・やらざるを得ない環境を作るのもモチベーションを上げるのによいです。
環境を変えることは、日頃の習慣を変えるのにとても効果的ですね。
色彩検定を合格するまでの勉強方法STEP3
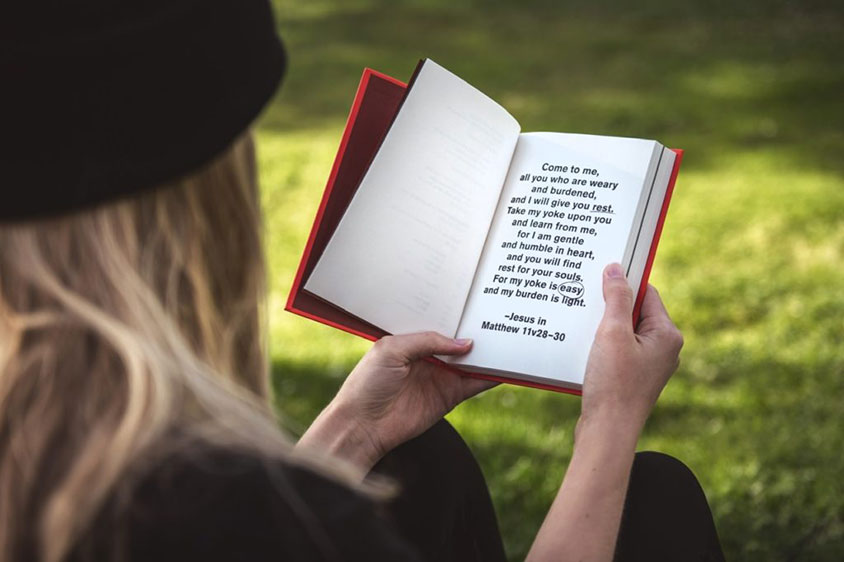
色彩検定を合格するまでの勉強方法STEP1
色の種類をとにかく見て暗記しよう
かならず出題されるカラーの選択は、瞬間的に色を覚える特殊能力でもない限り、
どうしてもその色の種類のことを見て暗記しなければ覚えられません。
似たような色がまた多いです。
「バーントシェンナ」や「ローシェンナ」という色があるのですが、馴染みがない名前ですよね。
上の2色はイメージとしては茶色に近い色です。
色の覚え方は、色彩検定の専門書籍や色のアプリなどで覚えていきましょう。
【注意点】
色を表示するアプリを使う場合は、スマホのフイルムの色やスマホのカラー設定に気をつけてください。
ブルーライトのフイルムは黄色みがあると正しい色が分かりにくくなるためです。
アプリや専門書籍は資格取得を目指していなくとも覚えておくと、
クリエイティブな作業やパワーポイントでプレゼン資料を作るといった場面でタメになりますね。
色彩検定を合格するまでの勉強方法STEP2
配色パターンと色相環の図をマスターしよう
赤なら赤に合う色の配色は何か?
内容を覚えて、人に説明できるようになった時はもう合格が目の前まできています。
3級では配色の基本が出題され、2級では応用が入りトーンの配色方法の名称、コントラストやアクセントといった言葉が出題されます。
色彩検定を合格するまでの勉強方法STEP3
ファッション、インテリア系を暗記。とにかく過去問を解く!
シンプルですが、資格合格の専門書籍で過去問・模擬問題を解いていきます。
ファッション・インテリアの分野は画像付きで紹介されます。
元々洋服や家具に興味を持っている人であれば、雰囲気で「コレが答えかな?」と分かるかと思います。
インテリアなどは暗記ものが気持ち多いので、公式のテキストを読みこんでいきましょう。
資格の取得後に感じたメリット【自分の経験談】
色彩検定の資格取得後のメリット
色彩検定の資格を取って得られた効果は
・イラストやデザインなど制作全般の配色にあまり悩まなくなった。
・同僚や部下の制作物の添削を知識に基づいて行えるように成長。
・洋服やインテリアは目的を考えて配色を選んで購入するようになる。
といった変化がありました。
残念ながら、国家資格と比べてインパクトは弱いものです。
「資格を取ってて良かったな」
と思ったタイミングは自分のスキル・知識として、カラー配色について自然と人に説明ができた時ですね。
「この配色は可読性が良くないから、色の明暗の差を付けよう」など
理由づけをした提案や改善案が出せる・共有できるようになったことは、
チームの作業効率を上げるのにとても役立ちました。
-
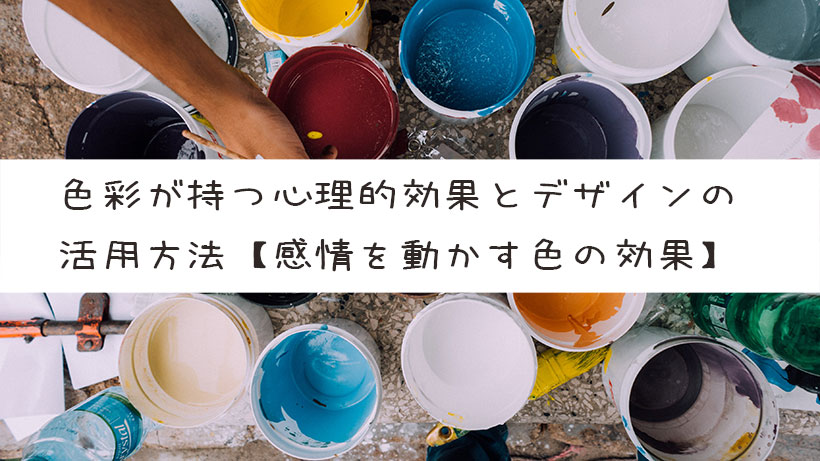
-
色彩が持つ心理的効果とデザインの活用方法【感情を動かす色の効果】
・WEBやイラスト、広告デザインでイメージカラーに悩んでいる ・ダサいファッションやカラーセンスと絶対に言われたくない ・色彩検定の勉強をしている、色に興味がある といったデザインやイラスト方面の疑問や悩みを解消していきます。 & ...
続きを見る
記事のまとめ
あらためてですが、
色彩検定はカラーコーディネートの知識を論理的に勉強して、
自分のスキルに変えることができるのが強みです。
資格合格の方法は「独学で1ヶ月真剣に勉強する!」です。
合格ラインは
各級満点の70%前後の正答率"で合格になります。
今回の記事が色彩検定の試験のきっかけ・勉強のモチベーションを上げる機会になればうれしいです!
ではまた。